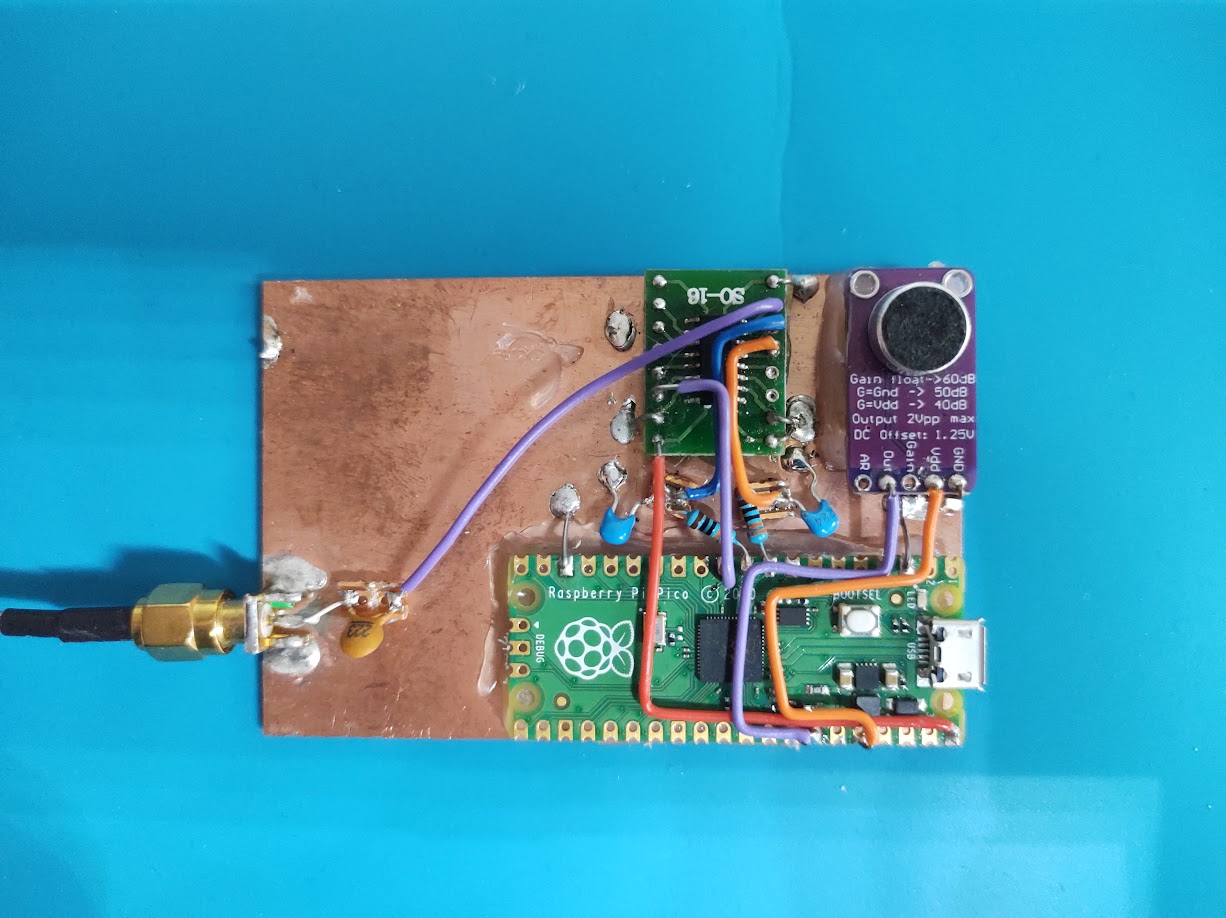先週末は、RTTY界の春祭り(かな?)、CQ WPX RTTYでした。
しばらくQRTになるので、ちょっとだけ参加してみました。
Contest: CQWPXRTTY
Band QSOs Pts WPX Pt/Q
7 7 18 7 2.6
14 2 3 2 1.5
21 23 67 16 2.9
28 43 115 36 2.7
Total 75 203 61 2.7
Score: 12,383
「たったの75QSOですか!」と言われそうですが、正味4WほどのQRP運用でした。
使用したトランシーバはHermes Lite 2 です。
送受信のバランスも良く、価格もリーズナブルだと思います。HF帯SDRの入門機としてお勧めできます。
春節休暇中ですが、在庫有りのようです。
https://www.makerfabs.com/hermes-lite-2.html
もちろん、免許もTSSの保証でスムーズに降りました。
話がそれますが、TSSの保証業務終了はアマチュア無線にとって災難ですね。
という訳で、交信いただいた皆さんには、ただただ感謝するばかりです。
QRP参加の訳は、純粋な興味が半分。
残り半分は、スキマーやドップラーグラムの受信機類を止めたくなかった(めんどくさかった?)のです。
4Wなら、もろに飛び込んでも壊れることはまず無いので。
アンテナは直径0.65Mのスモールループ(2N5109 x2)、受信機はRedPitaya 16です。
で、そのスキマーですが、補足したCQ局とすべてQSO出来たら・・・という、究極のタラレバをやってみました。
自分がアップしたスキマーのデータをPSK ReporterからADIF形式ダウンロードし、
WPX RTTY標準のCABRILLOに変換して、SH5で分析したものです。
なお、PSK Reppterから帰ってきたのは6,353件(CQ)ですが、スキマーのログでは11,965件になっていました。
差は、短い間隔での複数解読や明らかなエラーなどで弾かれた物のようです。
Main
補足数は6,353件、重複は4,778件、正味は1,575件。
エンティティは91でした。
アレっ、自分のロケーター間違えてますね。お恥ずかしい orz
Summary
21MHzが稼ぎ頭でした。7MHzも健闘していますね。
14MHzはノイズが多く今一つでした。アンテナの所為かもしれません。
Log
レートのビークは、土曜の夕方でした。
ほとんどDupeですが、なかなかの壮観です。
Callsigns
ユニークコールは930件でした。が、よく見ると
YE1G, YE1GX, YE1GXQのような誤解読がかなりあります。
JARTSに届く本物のログにも同じ傾向がありました。
ただ、あくまでも照合可能な「誤り」であり、「水増し」や「架空」はありませんでした。
Rates
10分間のピークは、ハイバンドで北米がオープンした日曜の朝9時半頃。
1時間のピークは、ハイバンドでEUがオープンした土曜の18時台でした。
Qs by minute
Qs per station
5バンドで見えていたのは、21局でした。
PCの負荷
はじめてスキマーを動かしたとき、面白いと思ったのが信号の数でCPUの負荷が大きく変動することです。
以前使用していたWindows 7時代のPCがダウンしてしまい、1月半ばに某オクでWindows 10時代のノートPCを入手していました。
昔はインストールも楽しかったのですが、だんだん億劫になって延し延しにしていました。
で、開始直前に慌ててスキマーを入れていたのです。(その時に、グリッドを間違えたようです)
最初の設定で、バンド幅(解読範囲)を狭くしてしまったので、スタート直後のCPU温度(ピンク)が低めです。後で気が付いて、何度か調整して広げたので温度が上がっています。
深夜は気温の低下もありますが、信号が少なくなって負荷(緑)が下がり、温度も下がっています。
ハイバンドの北米オープンと共に、負荷と温度が急上昇しました。
なお、電源の設定でCPUのマックスを99%にしています。100%にするとオーバークロックが機能するらしく、冷やし切れなくなる場合があります。
最後に、最近JAからのスポットが少ないですね。
隠れスキマーは少なくないと感じますが、本気で参加している局にとっては、ライバルに塩を送る必要はないので、まぁ仕方ないですね。hi